1971年7月30日の雫石事故
1971年7月30日、岩手県雫石町の上空で、全日空58便と航空自衛隊のF-86F戦闘機2機が訓練中に衝突し、民間機が墜落。162名(乗客155名+乗員7名)が命を落とした、日本の航空史に残る未悲劇——それが「雫石事故」です。
この事故には、当時の日本の航空政策、軍民の空域調整、そして「人の判断の重さ」が深く関係していました。特に重要なのが訓練中の教官の判断、そして後の政治的対応としての中曽根康弘防衛庁長官(当時)の行動です。
教官の指示ミス
この事故で問題視されたのは、航空自衛隊の訓練機(F-86F)の教官の指示でした。
● F-86F戦闘機は訓練生と教官が編隊飛行を行いながら、模擬空中戦(ドッグファイト)の訓練を実施していました。
● 訓練中に教官が、訓練生の視界確保や安全確認を怠り、全日空機の接近に気づくのが遅れました。
● 決定的だったのは、教官が訓練生に「反転して敵役(教官機)を追え」と指示したタイミングで、訓練生が反転し、直後に全日空機と衝突してしまったことです。
● 通常であれば、教官が周囲の安全確認(クリアランス)をしたうえで指示を出すべきところ、それがなされていなかったと指摘されました。
この行為は、当時の自衛隊内の訓練慣行や緊張感の欠如、さらには民間機と軍用機の空通常、戦闘機の訓練空域は事前に民間航空機との調整が取られるべきですが、当時の制度や監視体制はまだ不完全。空域管理のずさんさとともに、教官の状況認識不足が重なってしまったのです。「まだ訓練中の若者に高度な判断を任せすぎた」として、後の裁判でも厳しく問われることになります。
教官の過失と判決
-
教官は禁錮3年・執行猶予3年の有罪判決。
-
航空自衛隊を退職し、その後はパイロット職に復帰することなく、2005年に亡くなりました。
- 心に消えない傷とともに人生を歩んだ一人でした。
そしてこの事故には、もう一つ語り継がれるべき人生があります。
それが、F-86Fに乗っていた訓練生です。
責められ、裁かれ、それでも生きた
事故後、彼は逮捕され、業務上過失致死と航空法違反で起訴されました。まだ若い訓練生である航空自衛隊に夢を託した一人の青年にとって、その後の道はあまりにも険しいものでした。
第一審では禁錮2年8か月の実刑判決。
けれども控訴審と上告審で無罪が確定します。
事故は単なる「個人の過失」ではなく、組織や教育体制、そして人間の限界が複雑に絡んだものであったと認められたのです。
それでも彼の心には、消えることのない傷が残ったはずです。自分が生き残ったという事実は、誰よりも彼自身を苦しめたことでしょう。
人命救助という使命
彼はその後、航空自衛隊に残り続けました。しかし、戦闘機パイロットから救難機(救助ヘリや輸送機)パイロットへと転向します。
「人を助ける仕事をしたい」
「命を救うことで、自分に課せられた意味を見出したい」
そういう思いがあったのかもしれません。
2003年10月、彼は定年退職まで勤め上げました。空の厳しさを知る者として、多くの命を救い、生き続けたのです。
中曽根康弘防衛庁長官の対応
当時、防衛庁長官を務めていたのが後に首相となる中曽根康弘氏でした。
事故直後、中曽根氏は自衛隊側の責任をある程度認めながらも、世論や遺族感情に強く配慮する形で対応しました。
特に注目されたのは、次のような姿勢と発言です。
-
「自衛隊員にも厳しい指導が必要」
-
「民間機の安全が最優先であるべき」
-
「自衛隊の訓練空域の見直しを検討」
一方で、自衛隊への批判が過熱しすぎることを懸念し、防衛庁として制度的な問題にも言及するバランスを取った対応でした。
事故後、中曽根氏は軍民の空域分離や航空管制のあり方、自衛隊の訓練方法の見直しなどを進めるきっかけを作りました。これが後の日本の航空安全政策や自衛隊改革にも影響を与えたと言われています。
雫石事故が遺した教訓
1. 人間の判断ミスは必ず起きる
→ 教官であっても「見落とし」「確認不足」は起きる。だからこそ訓練やマニュアル、制度で安全を補完する必要がある。
2. 軍民の空域調整と情報共有の重要性
→ 自衛隊と民間航空の空域の区別や訓練空域の設定が重要。
1971年の雫石事故は、航空自衛隊の教官が訓練生に安全確認を怠ったまま反転指示を出し、全日空機と衝突したことで発生しました。155名が犠牲となったこの事故を受け、日本の航空法や空域管理は大きく見直されました。
特に、軍(自衛隊)と民間航空の空域の使い方や情報共有が制度化されました。1973年には航空法改正により訓練空域の設定や管理が厳格化され、防衛省と国交省の間に「空域調整委員会」が設置されました。さらに、レーダー情報の共有や訓練空域への民間機の立ち入り制限などが導入され、現在の航空安全の基盤が築かれました。

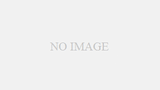
コメント