- NTT株は買いか?わかりやすく分析!
- 北尾さんと言えば、フジテレビ助けた人か?
- アメリカで発行のクレジットカードを日本で利用してます。日本でクレジットカード発行するより、デビッドカードかプリペイドクレジットカード?の方が手続きは楽でしょうか
- 中国はアメリカ国債売って金買ってますね
- 実家に帰ると75才の母が銀行窓口や証券会社数社で本人にも何に投資してるかもわかっていない投資信託やファンドラップに多数契約していることがわかりました。しかもマイナスばかり出ています。本人はネット証券をしていないので手数料のバカらしさをわかっていません。どう整理していけば良いと思いますか。アドバイスいただけるとありがたいです。。。
- 農林中金が米国債でド偉いことになってますよね
- SMBC日興証券とdポイント
- NISAやるには専用口座作らないといけないんですね
- SlimS&P500の信託報酬引き下げ
- 大切な真実はスミッコに存在する
- 岡元兵八郎さんのS&P500推し
- 住信SBIネット銀行の圧倒的な強み
- SFCはカード持ってなくても維持できる?
- 半年ごとに日本と外国を行ったり来たりする場合は、海外在住扱いになるのかしら?
- 三菱商事はまだ早いですよ RSIが50%切ってない まだ下がります
- 今なら、PTS(私設取引システム)で2454.3円で買える
- ベア3.8で去年大負けしました
- キリン 下落が止まらないですよね
- クロスボーダー税制に詳しい方いらっしゃいますか?
- 次の円安のピークは2032年くらい、その時は1ドル200円くらいだと思う
- SBIの入金の方法があまりわからなくて
NTT株は買いか?わかりやすく分析!
財務データから見るNTTの現状
| 指標 | 値 | 解説 |
|---|---|---|
| PER(株価収益率) | 約12倍 | 割安水準(一般的に15倍以下は割安) |
| PBR(株価純資産倍率) | 約1.2倍 | ほぼ適正(1倍以上なら資産価値以上の評価) |
| ROE(自己資本利益率) | 約11% | 良好な収益性(8%超えは優秀) |
| 配当利回り | 約3.2% | 高配当(銀行預金より有利) |
| 自己資本比率 | 40〜50% | 財務的に健全 |
ポイント
- PER 12倍:割安で、株価が上がる余地あり。
- PBR 1.2倍:過去と比べても適正水準。
- ROE 11%:収益性が高く、株主資本を効率的に活用。
- 配当利回り 3.2%:安定した配当を得られるのも魅力。
➡ 総じて、財務状況は安定しており、「ディフェンシブ銘柄」として優秀。
NTTの強み
通信業界の絶対的な安定性
通信は社会インフラ:インターネット、スマホ、データ通信など、NTTグループは日本の通信基盤を支える存在です。
-
- ドコモ:日本のスマホ通信シェア約40%
- 光回線(NTT東西):日本の主要な固定回線インフラ
政府が大株主(安定性が高い):NTTは政府が約30%の株を保有する国策企業。
-
- メリット:安定性が高い
- デメリット:規制が強く、自由な経営がしにくい
成長余地あり
- 5Gの普及
基地局の設置が進み、安定収益が期待できる。 - 光回線の契約増
固定回線需要が増え、業績を支える。 - 新技術IOWNの推進
次世代通信技術 IOWN による成長戦略も評価される。IOWNは「光」を活用した次世代通信技術で、超高速・超低遅延・省エネルギーを実現し、NTTが中心となり、ソニーやインテルなどのグローバル企業とも協力
➡ 通信インフラという安定性を持ちながら、成長分野にも進出中。
IR BANKのデータ
安定配当を狙う長期投資に適している
配当利回り3%超は魅力的で、NISA口座での長期保有に向く。
グロース株としては微妙
PERが割安でも、急成長は期待しにくい。
➡ 「安定した配当をもらいながら、堅実に資産を増やす人」に向いた銘柄。
ベースは個別株よりeMaxis slim sp500や全世界株などのインデックス投資で資産を15年以上保有して増やす戦略で、その上で高配当株投資としてNTT株は「高配当を得る目的」で買うのはアリ。
NTT株は買いか?
- 安定した配当を狙う投資家
NISA口座で長期保有を検討すると◎。 - 通信インフラの安定性を評価する人
景気に左右されず、堅実に資産を増やしたい人。
❌ 避けるべき人
- 短期で値上がり益を狙う人
グロース株ではないため、大きなキャピタルゲインは期待できない。 - 個別株よりインデックス派の人
NTT株単体より、TOPIXやS&P500などに投資したほうが分散効果あり。
- 安定性◎:通信インフラという強みと、政府保有の安定性。
- 成長性△:IOWNなどの成長戦略はあるが、急成長は難しい。
- 配当利回り◎:3%以上の配当は魅力的。
➡ 結論:「高配当+安定性」を求める人には適した銘柄。ただし、短期で値上がりを狙う人には微妙。NISAで長期保有し、配当を楽しむのがオススメ。
NTTは良いかも! と思われた方の意見は正しいです。ディフェンシブ株として安心感のある投資先です。
→で、自分で1株買ってみる(SBI証券へ、ついでに銀行との連携をお見せする)
日本の法律では、特定の銘柄を「買い推奨」する行為には厳しいルールがあり
✅ 投資助言業の資格が必要(「投資助言・代理業」の登録なしに具体的な売買推奨をすると違法)
✅ 証券会社や金融機関以外の人が「買え」と断言すると、誤解を招く可能性がある
✅ 「風説の流布」「相場操縦」とみなされる可能性がある(相場に影響を与える発言は規制対象)
具体例:「買い!」と断言できない代わりに…
❌ 「この株は絶対上がる!」 → NG(誤解を招く)
⭕ 「この銘柄は○○の理由で成長性が期待できる」 → OK(事実に基づいた解説)
北尾さんと言えば、フジテレビ助けた人か?
北尾さんとフジテレビの因縁
北尾吉孝氏(SBIホールディングス社長)は、単なる「フジテレビを助けた人」ではなく、2005年のライブドア vs フジテレビの買収劇で重要な役割を果たした人物。
堀江貴文 vs フジテレビ・北尾さん
2005年、堀江貴文さんがライブドアを率いて、ニッポン放送を買収。
ニッポン放送はフジテレビの筆頭株主だったため、ホリエモンがこの会社を支配すれば、フジテレビを間接的に支配できるという構図でしたが、ここで登場したのが北尾さんで、SBIホールディングスの支援のもと、ホワイトナイト(救済役)としてフジテレビを守る側に回りました。
結果、フジテレビはライブドアの影響を排除し、買収防衛に成功し、その後、ホリエモンは証券取引法違反で逮捕。ライブドアは崩壊しました。
北尾さんは「フジテレビを救った男」でもあり、「堀江貴文を追い詰めた男」でもあるにもかかわらず、今の北尾さんは、ホリエモンの宇宙事業「インターステラテクノロジズ」に投資しています。
日枝久体制と個人投資家の動き
一方、現在のフジテレビは、2005年当時とは大きく状況が異なり、「日枝久(元会長)」の影響力が注目を浴びています。業績や財務諸表を見ると、フジテレビはメディアというより不動産会社といっても過言ではありません。
日枝氏は、1980年代からフジテレビの経営を握り続け、現在も影響力を持つ「フジテレビのドン」とされています。海外の投資家からも「独裁者」と批判されることがあり、フジテレビの改革を阻む存在とも言われていますが、フジテレビは変わろうとしています。そして、改革を後押しする個人投資家が増え、フジテレビ株を買い集めています。
フジテレビの株主総会で日枝久を追い出せる?
実際に個人投資家はどの程度の影響力を持っているか?「堀江貴文の仲間がフジメディアHDの大株主になったらしい」とコメントがあり調べてみました。「大株主」となるには 5%以上の株式保有 が必要ですが、現時点でそのような報道はありませんが実際はわかりません。彼の影響を受けた投資家が動いている可能性はありますよね。
フジ・メディア・ホールディングス(4676)の株主構成
→フジテレビの株価見てみる(SBI証券)
フジテレビの大株主
✅ ニッポン放送(33.4%) → フジ・メディアHDの筆頭株主(フジテレビを実質支配)
✅ みずほ信託銀行(信託口) → 約6%
✅ 日本マスタートラスト信託銀行(信託口) → 約5%
✅ 外国人投資家(合計20%前後)✅ 個人投資家も一定数存在
日枝久を追い出せる?
✅ 株主総会で取締役の交代には「議決権の過半数」が必要
✅ 現在のフジHDの経営陣は安定株主が多く、日枝氏を排除するのは容易ではない
✅ 個人投資家+外国人投資家が団結すれば可能性はあるが、現状は難しい
フジテレビの業績
フジテレビは潰れる?➡ その可能性は極めて低い。
現在、フジテレビの本業(テレビ放送)は厳しいですが、不動産事業(サンケイビル・ホテル事業)が好調です。
✅ 自己資本比率:約70%(2023年時点) → 財務的に非常に安定
✅ サンケイビルの収益貢献 → テレビが赤字でも、ビル収入で補填できるので、フジテレビは「不動産会社」としては優良企業です。
北尾さんの存在
「北尾さんがそんなことするはずないですよね!」その通りで、2005年の買収劇ではフジテレビを守った北尾氏だが、現在のフジテレビ改革には関与していませんが、北尾氏は現在も積極的に投資を行い、ホリエモンの宇宙事業を支援するなど、未来を見据えた戦略を取っています。フジテレビが本当に変わるなら、それは個人投資家の力によるものかもしれなくて
、2005年に買収劇を繰り広げた「ライブドア vs フジテレビ」の決着が、18年越しに違う形でつくのかもしれないと言われています。
フジテレビの未来、そして個人投資家の戦い
現在のフジテレビは、かつてのような絶対的な影響力を持つテレビ局ではなくなったことは明らかで、YouTubeやNetflix、Amazon Primeといった新しいメディアにより、地上波テレビは視聴率・広告収入ともに苦戦を強いられています。フジテレビは単なる「テレビ局」ではないと言っても良くて、むしろ、サンケイビルなどの不動産資産を活かし、経営を安定させている「総合メディア・不動産企業」と言えます。
個人投資家がフジテレビを変えることはできる?
可能性はゼロではない
フジテレビの大株主には外国人投資家(約20%)も含まれており、経営改革を求める動きは今後強まる可能性が大きく、外国人投資家と国内の個人投資家が連携すれば、経営陣への圧力が高まり、フジテレビの変革が加速するかもしれない。
敵は日枝久だけではない
フジテレビの「問題」とされるのは、日枝久氏の影響力だけではなく、旧態依然とした企業体質そのもので
✅ 内向きな組織運営
✅ 若手の挑戦が通りにくい社風
✅ デジタル戦略の遅れ
こうした問題を変えるには、トップの交代だけでは足りず、組織全体の意識改革が必要と言われています。
アメリカで発行のクレジットカードを日本で利用してます。日本でクレジットカード発行するより、デビッドカードかプリペイドクレジットカード?の方が手続きは楽でしょうか
日本での短期滞在や一時的な利用であれば、アメリカ発行のクレジットカードを使用することも可能ですが、長期滞在や頻繁な利用を予定している場合は、日本のデビットカードやプリペイドクレジットカードを取得する方が手続きも簡単で、日常的な利用に適している可能性が高いです。
最終的な選択は、滞在期間、利用頻度、利用目的によって異なりますので、ご自身の状況に合わせて判断することをおすすめします。
アメリカ発行のクレジットカード
アメリカで発行されたVisa、MasterCard、American Expressのクレジットカードは、日本の多くの場所で利用可能ですが、以下の点に注意が必要です
1. 為替手数料: 支払いの際に為替レートと手数料が適用されます。
2. 支払い方法: アメリカの銀行口座からの支払いが必要で、日本の銀行口座から直接支払うことはできません
3. 利用可能店舗: 大手チェーン店やデパートでは使えますが、小規模店舗や公共交通機関では現金の方が便利な場合があります。
デビットカードとプリペイドクレジットカード
日本でデビットカードやプリペイドクレジットカードを発行する方が、手続きが楽です
1. 簡易審査: クレジットカードと比べて審査が簡単で、短期間で発行できます。
2. 日本円での決済: 為替変動のリスクがなく、手数料も抑えられます。
3. 日本の銀行口座との連携: 日本の銀行口座から直接チャージや引き落としができます。
中国はアメリカ国債売って金買ってますね
中国はアメリカの国債を人質にしている!?
「世界最強の経済大国はどこか?」と聞かれれば、アメリカですが、そのアメリカ経済の「急所」を握っているのが中国だと知っている人は少ないと思います(出典:ロイター通信)
中国は長年にわたり「アメリカ国債」の最大の保有国で、2024年時点でも約7,770億ドル(約120兆円)もの米国債を持っていて、日本は世界第2位です(約1兆1000億ドル)
では、なぜ中国はこれほど大量の米国債を保有しているのか?
そして、近年、その保有額を減らしながらも、なぜ完全に手放さないのか?
その裏には、アメリカ経済を揺るがす可能性のある 「金融戦争」 のシナリオが隠されていると言われています(出典:ロイター通信)
中国はアメリカの国債を大量保有しているのか?
① 貿易黒字の運用先
中国は長年、アメリカとの貿易で巨額の黒字を計上し、その利益を「安全資産」として運用するために、流動性が高く信用度の高い米国債を大量に購入
人民元の安定化
米国債を大量に保有することで、中国は 為替市場で人民元をコントロールしやすくなり
米国債を売却すれば米ドル安・人民元高に、逆に購入すれば米ドル高・人民元安に誘導できるからです
つまり、アメリカ国債は、中国にとって「金融政策の武器」になっています
アメリカへの影響力を持つため
中国が米国債を大量に売却すれば、アメリカ国債の価格は暴落し、金利は急騰するので
これは アメリカ経済にとっての大打撃 となるため、中国は「アメリカに対する交渉カード」として米国債を利用できます
中国は米国債を売り始めている
近年、中国は米国債の保有額を徐々に減らしています
2022年には 1兆ドルを超えていた米国債保有額は、2024年には7,770億ドル(約120兆円)にまで減少しました
この背景には、次の3つの要因があります
❌ ① 米中貿易戦争の激化
米中の関係は悪化の一途をたどっており、中国は「アメリカ経済に依存しすぎない戦略」にシフトし、米国債を減らし、他の資産に分散投資することで、リスクを回避しています
❌ ② 外貨準備の多様化
中国は米ドルの比率を減らし、金(ゴールド)やユーロ、人民元建て資産への投資を増やし
、中国人民銀行は2022年以降、毎月のように金の購入を増やしています
❌ ③ アメリカ国債のリスク増大
米国の財政赤字は膨張し続け、金利も上昇しているので
「アメリカがいつかデフォルトするのでは?」という不安から、中国は米国債の保有を減らしていると言われています
「米国債を売る」という行動は、中国の「アメリカ依存脱却」の戦略の一環なのです
それでも中国は米国債を完全に手放さないワケ
「だったら、中国はすべての米国債を売ればいいのでは?」と思うかもしれないけれど、中国がアメリカ国債を完全に手放すことは、不可能でその理由は
米国債は世界最大の金融市場であり、売りたくても売れない
米国債は「世界一の安全資産」であり、流動性が高いため、投資資金の置き場として最適。
もし一気に売れば、市場が大混乱を起こし、中国自身もダメージを受けることになる。
アメリカ経済を不安定にするのは、中国にとってもリスク
米国債を一気に売れば、アメリカの金利が急上昇し、景気が冷え込むけど、アメリカ経済が崩壊すれば、中国の輸出にも大打撃が及ぶため、自爆行為となります
ETFを通じた「間接保有」
中国は直接的な米国債の保有を減らしているが、ETF(例えばAGGなど)を通じた「間接的な米国債投資」も行い始めています
これは、米国債を手放しながらも市場の流動性を維持しつつ、リスクを分散する戦略とも考えられています
中国は依然として約120兆円の米国債を持ち、アメリカ経済の急所を握っている
米中対立の激化により、徐々に米国債を売り、金や人民元建て資産へシフト中
一気に手放せば中国自身もダメージを受けるため、ETFを通じた間接投資
「アメリカが崩れれば中国も崩れる」——この緊張状態は、まさに「金融戦争」で、中国がどこまで米国債を減らし、どんな資産に移行するのかが、世界経済のカギを握っています
実家に帰ると75才の母が銀行窓口や証券会社数社で本人にも何に投資してるかもわかっていない投資信託やファンドラップに多数契約していることがわかりました。しかもマイナスばかり出ています。本人はネット証券をしていないので手数料のバカらしさをわかっていません。どう整理していけば良いと思いますか。アドバイスいただけるとありがたいです。。。
銀行や証券会社でよくわからないまま高額な投資商品にお金を預けてしまい、損失を抱えている……ってまじですか!!!ってことで、憤りを感じたので調べてみました。
銀行や証券会社の担当者や保険営業マンって高齢者をターゲットにしていて、親身になってくれるのを「信頼できる人」と思い、手数料の高い商品ばかりを買わせるってひどいです。
まず、現状を把握しましょう
お母さまが契約している投資商品のリストを作ります
銀行や証券会社で契約した投資信託やファンドラップの内容を正確に把握することが最初のステップで、以下の情報を整理してみてください。
確認すべきポイント
- 商品名・契約日
- 投資額・現在の評価額(損益)
- 手数料(購入手数料、信託報酬、解約手数料など)
- 毎月の分配金(ある場合)
- 「ファンドラップ」なら運用管理手数料の割合
ファンドラップは、長期的に見ると資産を大きく削る要因になります。
リスト化することで「解約すべき商品」と「保有を続けてもよい商品」を判断しやすくなります。
次に不適切な勧誘がなかったかをチェックしましょう
高齢者に対する金融商品の販売は、日証協(日本証券業協会)や全銀協(全国銀行協会)のガイドラインで厳しく規制されています。
もし、以下のような勧誘があった場合、不適切な販売(場合によっては「詐欺的勧誘」)に該当する可能性があります。
高齢者への不適切な勧誘の例
- 「リスクはほとんどない」「安全な商品です」などの説明があった
- 投資の知識がないのに、リスクの高い商品を勧められた
- 契約を急かされたり、しつこく勧誘された
- 本人が十分に理解しないまま契約していた
- 家族に相談させてもらえなかった
これらに当てはまる場合、証券会社や銀行に苦情申し立てが可能です。
まずは無料相談から始めましょう
- 消費生活センター(188)いやや
→ 金融トラブルの相談を受け付けており、解決策をアドバイスしてくれます。 - 日本証券業協会(日証協)・全国銀行協会(全銀協)
→ 銀行や証券会社の不適切な販売について相談可能。金融商品あっせん相談センター(FINMAC)電話番号: 0120-64-5005 - 金融ADR(裁判外紛争解決機関)
→ 金融庁の指導のもと、金融機関との和解交渉を行う機関。1. 証券・金融商品:FINMAC(上記日証協と同じ)2. 銀行:全国銀行協会相談室(上記全銀協と同じ)3. 保険:
– 生命保険:生命保険協会 生命保険相談所(東京)
電話番号: 03-3286-2648
– 損害保険:日本損害保険協会 そんぽADRセンター
電話番号: 0570-022808
有料相談
- 全国銀行協会(全銀協)全国銀行協会相談室
電話番号: 0570-017109 または 03-5252-3772
受付時間: 月~金曜 午前9時~午後5時(祝日および銀行の休業日を除く) - 貸金業:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
電話番号: 0570-051-051
返金や契約解除が可能?
過去の事例では、不適切な勧誘が認められた場合、一部または全額返金されたケースもあります。
証券会社や銀行に直接「説明不足があった」と主張し、契約解除を申し入れることも可能です。
裁判をした場合のコストは?
裁判にかかる費用の目安
- 弁護士費用:着手金 50万円〜100万円(成果報酬あり)
- 訴訟費用:10万円〜30万円(印紙代・郵送費など)
- 総額:100万円以上かかる可能性も
裁判をするかどうかは、損失額と弁護士費用を比較しながら慎重に判断が必要で、金融ADR(裁判外紛争解決機関)を活用すれば、費用を抑えつつ和解交渉ができる可能性があります。
過去の事例と政府・証券会社の補償について
- 過去に、高齢者への不適切販売が問題視され、証券会社が自主的に返金対応したケース があります。
- 証券会社や銀行の「苦情窓口」に相談すると、和解の形で返金される可能性も。
- 政府の補償は基本的にないが、行政指導が入ることで証券会社側が対応を変えることもある。
✅ まずは契約内容をリスト化し、損失額と手数料を把握する。
✅ 不適切な勧誘がなかったかをチェックし、証券会社や銀行に申し入れをする。
✅ 消費生活センター・日証協・金融ADRに相談し、解決策を探る。
✅ 裁判を検討する場合は、コストと返金可能性を天秤にかけて判断する。
親の遺産は、もしかしたら自分の財産となる可能性もあり、逆に負債になる可能性もあります。(荒れ地を残された場合など)母親のためにではなく、自分の未来のために、今できることをひとつずつ一緒に進めていきましょう。
農林中金が米国債でド偉いことになってますよね
農林中金は米国債を大量に持っていたけど、金利上昇で損しているということで「え、米国債って安全資産じゃないの?」と思うかもしれないけど、金利の動き で私のように損しているように見えますが手放さず配当金をもらい続け上がったタイミングで売るということも可能です。
農林中金とは
農林中央金庫(農林中金) は、JA(農協)や漁協などの資金を運用する「巨大な銀行」みたいな組織で日本最大の機関投資家の1つで、総資産は100兆円超。農協や漁協のお金を「安全に増やす」のが仕事です
農林中金はなぜ米国債を大量に買っていたの?
✅ 日本は 超低金利(ゼロ金利) で、安全な資産に投資してもほとんど利息がつかない
✅ アメリカの国債(米国債)は金利が高く、利息収入が大きい
✅ 農林中金は「米国債なら安全だし、利息ももらえて一石二鳥!」と考え、大量に購入
「金利上昇」で評価損が増えた
米国債は、金利が上がると価格が下がり
2022年から米国の金利が急上昇し、農林中金の持っている米国債の価値が暴落
その結果、「含み損(評価損)」が 数兆円規模 まで膨らんだ
2024年3月時点で、農林中金の含み損は「約2.8兆円」
2023年9月時点では約1.3兆円の含み損だったので、半年でさらに1.5兆円増加
米国債を一部売却して損切りし、(えっ??)「農協の経営にも影響が出るのでは?」と心配されています
売らなければ「評価損」は確定しないが、資金が動かせないリスクがあるので、農林中金は、全てを売るわけではなく、少しずつ損切りしながらリスクをコントロールしているそうです
「売らなければいい」は理論上は正しいけれど、実際には「資金流動性」と「金利リスク」の問題があるので、農林は損切りをし始めています。これらから学べることは、資産を分散すること(株と国債は逆の動きなので)国債で損切りするなら株で利益を得るなど方法があると考えられます。
ってことで農林が株に投資しているか調べてみました
株式ファンド(インデックス投資)
➡ S&P500などの指数連動型ETFに投資
➡ iSharesやVanguardのETF
日本国内の大企業株(インフラ・金融)
➡ 鉄道・通信・エネルギー・金融系の大手企業の株を保有(例:NTT、東京電力、三菱UFJなど)
➡ 配当収入が安定している銘柄を中心に投資している
海外のインフラ投資(不動産・エネルギー関連)
➡ REIT(不動産投資信託)や海外のインフラ企業にも投資
➡ 電力・ガス・水道など、景気変動に左右されにくい事業が多い
SMBC日興証券とdポイント
SMBC日興証券の「日興フロッギー」では、dポイントを使って株が購入できます。1ポイント=1円で利用可能なので、余っているdポイントを有効活用できます。さらに、マネックス証券もドコモと提携しており、こちらでもdポイントを使える仕組みがあります。
ポイント投資をするなら
- 日興フロッギー(SMBC日興証券)→ 100円から投資可能(dポイント利用OK)
- マネックス証券 → dポイント連携あり
- 楽天証券 → 楽天ポイントが使える
NISAやるには専用口座作らないといけないんですね
NISA(新NISAを含む)を利用するには専用口座が必要です。
証券会社でNISA口座の開設手続きをし、税務署の審査(通常1~2週間)を通過すると利用可能になります。
- 1人1口座しか持てない(証券会社の変更は可能)
- 2024年からの新NISAは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つに分かれました
- 非課税期間は無期限化(旧NISAは期間制限あり)
SlimS&P500の信託報酬引き下げ
eMAXIS Slim S&P500の信託報酬が0.0814%に引き下げられましたね
- 2024年に0.09372%から0.0814%へコストダウン
- 低コスト競争が激化中(楽天・SBIも対抗)
- 長期投資では、手数料の差が大きな違いに
「最安を目指す」というSlimシリーズの強みが活かされてます
大切な真実はスミッコに存在する
投資の世界では「広告で派手にアピールされない優良な商品」があります。
- 低コストのインデックスファンド(宣伝費をかけない)
- 配当の再投資の重要性(短期利益ではなく、長期で資産形成)
- 手数料の罠(ファンドラップや高コストの投資信託は要注意)
今までは海外の口座でしか買えなかったものや、富裕層しか知らなかったものが情報の民主化で手に入れられるので、みんなで使いましょう。
岡元兵八郎さんのS&P500推し
マネックス証券のチーフ・ストラテジスト であり、投資家向けに米国市場の分析や投資戦略を発信している人物で、ゴールドマン・サックスやバークレイズ証券などで米国株の運用・リサーチに従事し、米国市場に精通し、日本の投資家に米国株投資の重要性を伝えていて、現在、マネックス証券でストラテジストとして活動しています。
- 岡元兵八郎さんは「S&P500推し」ではなく「米国推し」でる
- S&P500や全米株式(VTI)を長期投資の選択肢として推奨している
- 米国市場のイノベーションの強さを信じ、長期的な成長を狙う投資戦略をとっている
住信SBIネット銀行の圧倒的な強み
ATM手数料が圧倒的にお得
住信SBIネット銀行:最大20回無料(ランク制)
SBI新生銀行:最大10回無料(ステージ制)
|
銀行 |
ATM無料回数 |
主な無料提携ATM |
|
住信SBIネット銀行 |
最大20回(ランク制) |
セブン銀行・ローソン銀行・イオン銀行・ゆうちょ銀行 など |
|
SBI新生銀行 |
最大10回(ステージ制) |
セブン銀行・ローソン銀行・イオン銀行・ゆうちょ銀行 など |
SBI新生銀行は、ランクが低いと無料回数が少なく、1回110円の手数料がかかることもありますが、住信SBIネット銀行なら 最大20回無料 なので、頻繁にATMを使う人には圧倒的に有利です。
振込手数料が圧倒的に安い&無料回数が多い
住信SBIネット銀行:最大20回無料(ランク制)
SBI新生銀行:最大10回無料(ステージ制)
|
銀行 |
振込無料回数(他行宛) |
条件 |
|
住信SBIネット銀行 |
最大20回(ランク制) |
ミライノカードなどを使えばランクアップ可能 |
|
SBI新生銀行 |
最大10回(ステージ制) |
条件クリアしないと無料回数が少ない |
住信SBIネット銀行は ランクを上げれば最大20回無料。SBI新生銀行より圧倒的にお得です
スマホアプリの使いやすさ
住信SBIネット銀行のスマホアプリ
✅ 使いやすい
✅ ワンタップで振込・残高確認が可能
✅ スマホ決済(Apple Pay、Google Pay)との連携がスムーズ
SBI新生銀行はアプリが使いにくく、振込時にストレスを感じることがあると言われていますが、住信SBI銀行ならハイブリッド預金でSBI証券と完全連携できます
✅ ハイブリッド預金 = SBI証券の「買付余力」に自動反映
✅ スイープ機能 = 証券口座と銀行口座の資金を自動移動
SBI新生銀行はSBI証券との連携が弱く、ハイブリッド預金のような仕組みがない…
SBI証券を使うなら住信SBIネット銀行一択で、 SBI証券クレカ積立のポイント還元が強いです
✅ 三井住友カード(ゴールドNL)なら 最大1.0%還元!
✅ 年会費無料のNLカードでも0.5%還元
SBI新生銀行は、クレカ積立の還元率で大きなメリットがない…
外貨預金・ドル転が簡単で手数料が安い
住信SBIネット銀行なら外貨運用もお得
✅ 為替手数料が激安!(米ドル1ドルあたり4銭~)
✅ SBI証券と連携して 外貨MMFや海外ETFへの投資がスムーズ
SBI新生銀行は為替手数料が高く、住信SBIネット銀行ほどのメリットなし…
7️⃣ 住宅ローンの金利がネット銀行トップレベル
住信SBIネット銀行の住宅ローンは業界最安クラス
✅ 変動金利:年0.32%(2024年2月時点)
✅ 全疾病保障が無料で付帯
SBI新生銀行は金利が高めで、無料の疾病保障もない場合がある…
✅ 住宅ローンを組むなら、住信SBIネット銀行が最もお得
住信SBIネット銀行の圧勝!
✅ ATM無料回数が 最大20回 → SBI新生銀行(最大10回)より圧倒的に多い
✅ 振込手数料が 最大20回無料 → SBI新生銀行(最大10回)より有利
✅ スマホアプリが 使いやすい → SBI新生銀行は微妙
✅ ハイブリッド預金+スイープ機能 → SBI新生銀行にはない
✅ SBI証券との クレカ積立&外貨運用が最強
✅ 住宅ローン金利が最安クラス&全疾病保障付き
⑬実家に帰ると75才の母が銀行窓口や証券会社数社で本人にも何に投資してるかもわかっていない投資信託やファンドラップに多数契約していることがわかりました。しかもマイナスばかり出ています。本人はネット証券をしていないので手数料のバカらしさをわかっていません。どう整理していけば良いと思いますか。アドバイスいただけるとありがたいです。。。
SFCはカード持ってなくても維持できる?
ANAカードを持っている人が海外駐在となる場合や、海外へ長期に滞在する場合
ANAカードについて
住所変更
– 1年以上の海外赴任の場合、ANAカードの登録住所を変更する必要があります
– 国内に家族が残る場合は、その住所に変更できます
– 単身赴任で現住所で家族が郵便物を受け取れる場合は、住所変更は不要です
2. 海外生活ヘルプデスク
– 三井住友カード(NL)の場合、海外生活ヘルプデスクに登録することで、海外赴任先に更新カードや利用明細を郵送してもらえます
– ただし、カードの種類や渡航先によっては申し込みできない場合があります
3. 利用明細:
– ウェブ明細に変更することをお勧めします
4. カード更新:
– 更新時期を確認し、必要に応じて対応してください
海外でのANAカードとSFCステータスについて
ANAカードを持っている人が海外駐在や長期滞在する場合
1. 現在のANAカードの継続利用可能ですが、為替手数料や海外利用手数料が発生する可能性があります(JALカードでは通常、海外での利用には為替手数料が発生し1.6%〜2.5%)
2. 海外専用ANAカードの取得:
- アメリカ赴任の場合、ANA CARD USAを申し込むことができます
– 年会費は70ドルで、カード利用1ドルごとに1マイルが貯まります
– 家族カードの発行は無料 - 中国赴任の場合
– ANA銀聯カードを発行可能で、中国での利用に適しています - 海外赴任サービスの利用
– ANAの海外赴任サービスを利用すると、ANA CARD USAの初年度年会費(70ドル)が無料
3長期滞在者向けのサービス
– ANAインターコンチネンタルホテル東京では、30泊の長期滞在プラン「ホーム・アウェイ・フロム・ホーム」を提供
4 リゾート会員権/タイムシェアの検討
– 頻繁に海外旅行をする場合、ANAの提携リゾート会員権やタイムシェアの利用も選択肢の一つです
海外赴任や長期滞在の際は、現地の法律や規制に従ってカードを利用することが重要です。また、渡航前にANAカードの海外利用設定を確認し、必要に応じて海外専用カードの申請を検討することをおすすめします。
海外でのSFCについて
1. ステータス維持
– SFC(スーパーフライヤーズカード)は、年会費を支払えば永久的にANA上級会員の資格を維持できます
2. ステータス獲得方法
– プラチナ以上のメンバーになるとSFCを取得できます(要申し込み)。
– 獲得条件は、プレミアムポイントのみ、またはプレミアムポイント+ANAカード/ANA Pay決済額+ライフソリューションサービス(LS)利用数の組み合わせで判定されます。
3. 海外でのステータス維持
– 海外赴任中もANAカードを使用し、プレミアムポイントを貯めることでステータスを維持できる可能性があります。
注意点として、海外転出時にマイナンバーカードは一時的に失効しますが、帰国時に必要となるため大切に保管してください。また、ANAカードの海外送付については、一部のカード(三井住友銀行キャッシュカード機能付カード、Oliveフレキシブルペイ、交通系IC機能付カードなど)は海外への送付ができない場合があります。
詳細については、全日空の公式ウェブサイトで最新の情報を確認することをお勧めします。
半年ごとに日本と外国を行ったり来たりする場合は、海外在住扱いになるのかしら?
半年ごとに日本と外国を行き来する場合、通常は海外在住扱いにはなりません。
1. 居住者の定義
日本の税法上、居住者とは国内に「住所」を有し、または現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人を指し、半年ごとの往来では、日本での滞在が継続的に1年未満となるため、通常は日本の居住者として扱われています
2. 生活の本拠地
居住者か非居住者かの判断は、単に滞在日数だけでなく、「生活の本拠」がどこにあるかによって決まるので、半年ごとの往来の場合、日本に家族や資産がある場合、日本が生活の本拠地と見なされています
3. 183日ルールの誤解
「183日海外にいれば日本の非居住者になる」という考えは誤解で、日本の税法では、外国に1年の半分以上滞在していても、生活の本拠が日本にあれば日本の居住者となる場合があります
4. 複数国での居住
半年ごとの往来の場合、日本と外国の両方で居住者扱いになる「双方居住者」となる可能性があり、租税条約に基づいて居住地が決定されることがあります。
半年ごとの日本と外国の往来では、通常は海外在住扱いにはならず、日本の居住者として扱われる可能性が高いです。ただし、個々の状況(家族の所在、資産の保有状況、職業など)によって判断が異なります。
三菱商事はまだ早いですよ RSIが50%切ってない まだ下がります
長期投資派なら、RSIを気にせず「配当利回り」「業績」「割安性(PER・PBR)」を見て判断し、短期トレード派なら、「RSI」「移動平均線」「出来高」などのテクニカル指標を活用して、より良いエントリーポイントを探るというのはどうでしょうか。「少しずつ買い増す」ことで、リスクを抑えて平均取得価格をコントロールするのも有効な戦略だと感じています。
✅ 長期投資なら、RSIにこだわる必要はない
もし10年以上保有するつもりなら、RSIが50%かどうかはあまり気にする必要なくて、業績・配当・事業の成長性を重視するほうが大切だと思っています
✅ 短期トレードなら、もう少し待ちます
短期で売買するつもりなら、RSIが50%を切るまで待つの戦略が大事で、他の指標と合わせて判断することが重要だと思います。
RSI(Relative Strength Index)
RSI(相対力指数) とは、株価の「買われすぎ」「売られすぎ」を判断するテクニカル指標 で、過去の一定期間(一般的に14日間)の株価の上昇・下落の比率を計算し、0〜100%の間で数値を出すものです。
RSIの計算式
RSI = (上昇幅の平均) ÷ (上昇幅の平均 + 下落幅の平均) × 100
RSIの見方
✅ 70%以上 → 買われすぎ(高値警戒) → 株価が下がる可能性がある
✅ 30%以下 → 売られすぎ(割安) → 株価が上がる可能性がある
✅ 50%付近 → 「上がるか下がるか微妙なライン」
まだ早い
RSIが50%を切っていないということは、まだ「売られすぎ」の水準ではないということで、株価はまだ下がる余地があるかもしれない ということで
- 「RSIが50%以上」 → まだ相場が本格的に下落していない可能性がある
- 「RSIが30%以下」 なら、過去のデータ的に「売られすぎ」で反発しやすい
- 「50%を切っていない」= まだ下落余地がある
つまり、「本当に安いところで買うなら、RSIが50%以下、理想は30%以下まで待ったほうがいい」 ということです
RSIは「テクニカル指標」
RSIは「短期的な売買判断」に使う指標なので、長期投資にはそこまで重要ではないと思っていて「RSIが30%以下なら買い」ではなく、PER、PBRなどを見る初心者なのです。
大型株は、RSIだけでは予測が難しいと言われ
時価総額の大きい企業は、テクニカル分析よりも、長期的な業績や配当利回りのほうが重要かもしれないので、短期トレードならRSIを気にすると思いますが、長期投資でずっと何十年も持ちるづける予定だと「割安かどうか」のほうが大事に感じています
最適な投資戦略
長期投資派なら、RSIを気にせず「配当利回り」「業績」「割安性(PER・PBR)」を見て判断し、短期トレード派なら、「RSI」「移動平均線」「出来高」などのテクニカル指標を活用して、より良いエントリーポイントを探るというのはどうでしょうか。「少しずつ買い増す」ことで、リスクを抑えて平均取得価格をコントロールするのも有効な戦略だと感じています。
今なら、PTS(私設取引システム)で2454.3円で買える
PTS(時間外取引)で、三菱商事の株が2454.3円で取引されているから、翌日の値動きを先取りできますが、流動性が低いので慎重に判断することが大事で、PTS価格が翌日の東証の始値と必ずしも一致するわけではないので、注意が必要。PTSを活用すれば、うまく安値で拾えることもありますが、慎重に判断して取引するのがベストと言われています。
PTS(私設取引システム)とは
PTS(Proprietary Trading System)とは、証券取引所(東証など)とは別の、民間企業が運営する株式取引システムのことで証券取引所が閉まった後でも株の売買ができるのが特徴
日本の代表的なPTS市場
✅ SBI PTS(SBI証券が運営)
✅ JNX(ジャパンネクスト証券が運営)
PTSの仕組み「なぜ東証の価格と違う?」
通常の株取引は、東証の取引時間(9:00〜15:00)で行われますが、PTSは「時間外」でも取引できる市場で、夜間にアメリカ市場の影響で株価が動く場合、PTSではそれを先取りして売買できます
PTSでの価格の動き方
✅ 「PTSで2454.3円で買える」と言うことは、東証の終値とは異なる価格で取引されている
✅ PTSの価格は、翌日の東証の始値に影響を与えることがある
✅ 流動性が低いため、大口注文が入ると価格が急変しやすい
✅ 買うべきケース
✅ 翌日の株価が上がる可能性が高いと判断した場合(例:良いニュースが出た後)
✅ 東証の終値よりも割安な価格で買える場合
❌ 買うべきでないケース
❌ 流動性が低く、思った価格で売買できないことがある
❌ PTSの価格が翌日の東証の株価とズレることがある
ベア3.8で去年大負けしました
「株価の下落に賭ける」のではなく、「資本主義の発展と企業の成長」という、先人たちの努力が積み上げてきた資本主義の成果に投資するほうが、合理的で確実な方法だと感じています。
私はベアのことまで知らなかったので、きっと小林さんは、いろんな経験をされているんだと思います。
ベア投資とは
投資をしていると、「相場が下がると利益が出るベア型投資」に興味を持つことがあるかもしれません。特に、経済が不安定なときや「今の株価は上がりすぎでは?」と感じたときに、ベア型の商品に手を出す人が多いと言われています。
しかし、ベア投資は難しく、多くの人が損をする仕組みになっています。本記事では、ベア投資の仕組みやメリット・デメリットを解説し、長期・分散投資でコツコツが良いことを考えていきます。
ベア投資とは
「ベア(Bear)」とは、相場が下がると利益が出る仕組みの投資商品です。通常の投資は株価が上がることで利益が出ますが、ベア型の投資では逆に株価が下がることで利益が出ます。
ベア型ETF(上場投資信託)
📌 日経平均ベア2倍ETF(1360)
📌 ダウ・ベア3倍ETF(SPXS) など
➡ 日経平均やS&P500などの指数が下がると利益が出るETFです。
⏩ 特徴
✅ 相場の下落時に利益が出る
✅ レバレッジ型(2倍・3倍など)は短期間で大きな利益も損失も出る
✅ 長期投資には向かない(逓減効果で不利)
② インバース(Inverse)型投資信託
📌 日経平均インバースファンド
📌 NASDAQ100ベアファンド など
➡ 株価指数が下がると基準価額が上がる投資信託です。
⏩ 特徴
✅ ETFと違い、投資信託なので1日1回基準価格が決まる
✅ 手数料が高めなものもあるので注意が必要
③ 先物・オプション取引
📌 日経225先物の売りポジション
📌 プットオプション(売る権利の購入) など
➡ 相場が下がると利益が出る本格的なヘッジ手法です。
⏩ 特徴
✅ 大きく下落したときに利益が出やすい
✅ 専門知識が必要で、初心者向きではない
✅ レバレッジをかけると損失も大きくなる
ベア投資のメリット・デメリット
✅ メリット
- 相場の下落時に利益が出せる
➡ 株式市場が暴落したときに大きなリターンを得る可能性がある。 - リスクヘッジに使える
➡ 株式の下落リスクを抑えるために一部をベア型にすることで、資産全体のリスク管理ができる。 - 短期トレード向き
➡ レバレッジを活用すれば、短期間で大きなリターンを狙える。
❌ デメリット
- 市場は基本的に右肩上がり
➡ 株式市場は長期的に成長するため、ベア型を持ち続けると負けやすい。 - レバレッジ型は逓減効果(ていげんこうか)で不利
➡ 価格が上下を繰り返すと、時間とともに基準価格が下がる性質がある。 - 逆張りは難しい
➡ 相場が「これから下がる」と予測するのは非常に難しく、多くの人は予想を外して損をする。
ベア投資派
✅ 「今の相場は上がりすぎだから、そろそろ下がるはず」
✅ 「大きく下落すれば、一気に儲かるかも」
✅ 「暴落に備えておきたい」
しかし、現実には「暴落する」と思っても、そのタイミングを正確に当てるのはほぼ不可能で、仮に一度成功しても、次も成功する保証はありません。
実際、多くの人が「短期間で得をした!」という気持ちでベア投資をして、大きな損失を出してしまうのが現実と言われています。
先人たちが築きあげた「資本主義の成長」
長期的に成功している投資家たちは、相場の一時的な上下ではなく、資本主義の成長そのものに投資をしています。
例えば、過去100年以上にわたり、アメリカのS&P500や世界の株式市場は右肩上がりで成長してきました。これは、企業が利益を生み出し、経済全体が発展しているからです。
「市場が下がることに賭ける」のではなく、「市場が成長し続けることで収益が上がる」ほうが、投資の成功確率は圧倒的に高いです。
✅ 短期の値動きを予想しようとしない(未来は誰にも分からない)
✅ S&P500や全世界株のインデックスファンドに長期投資(市場の成長に乗る)
✅ 「投資はギャンブルではない」と理解する(堅実に資産を増やす)
✅ コツコツ積み立てて資産を増やす(タイミングを気にしない)
ベア投資は難しい
ベア投資は短期的に大きく収益をあげる可能性がありますが、その分リスクも大きく、多くの人が失敗する投資で、長期的に市場の成長に投資をすることで、堅実に資産を増やすことができます。
「株価の下落に賭ける」のではなく、「資本主義の発展と企業の成長」という、人類の努力が積み上げてきた成果に投資するほうが、はるかに合理的で確実な方法です。
キリン 下落が止まらないですよね
クロスボーダー税制に詳しい方いらっしゃいますか?
日本の確定申告で外国税額控除を利用することで、クロスボーダー取引における二重課税を回避できる可能性があります
外国税額控除方式では、同じ所得に対する二重課税を防ぐことができます
1. 控除限度額があり、日本の税法で計算した外国所得に対する税額を超えて控除することはできません。
2. 適用には条件があり、すべての海外所得に対して自動的に適用されるわけではありません。
3. 租税条約の適用により、さらに税負担が軽減される可能性もあります
利用方法
1. 租税条約の活用
– 国家間で締結された租税条約を利用して、課税権の配分や税率の上限を設定
– 例えば、日本とシンガポールの租税条約により源泉税率を軽減できます。
2. 外国税額控除制度
– 外国で納付した税金を自国の税額から控除する制度です。
– 例えば、米国子会社の利益に対して支払った米国税を日本での税額から控除できます。
– ただし、自国の税法で計算した外国所得に対する税額を限度とします。
3. 外国子会社配当益金不算入制度
– 一定の要件を満たす海外子会社からの配当金について、その95%相当額を益金不算入とします。
– 例えば、海外子会社株式の25%以上を6カ月以上保有している場合に適用されます。
4. 移転価格税制の適切な運用
– 関連企業間の取引価格を独立企業間価格(Arm’s Length Price)に基づいて設定します。
– これにより、不当な所得移転を防止し、各国での適正な課税を実現します。
これらの方法を適切に組み合わせることで、クロスボーダー取引における二重課税のリスクを最小限に抑えることができます
クロスボーダー税制とは、国と国をまたいでビジネスをする時に関係する税金のルールのことで、日本の会社がアメリカで商品を売る場合や、日本の親会社が海外の子会社とやり取りをする場合などに適用されます。
1. 公平な取引
国をまたいで取引をする時、お互いの国で適切に税金を払うようにするルールです。
2. 移転価格税制
親会社と子会社の間で商品やサービスのやり取りをする時、適切な価格をつけるルールです。これは、税金を少なくするために不自然に安い価格や高い価格をつけないようにするためです。
3. 二重課税の防止
同じお金に対して二つの国で税金を払わなくてもいいようにするルールもあります。
4. 情報交換
国々が協力して、税金逃れを防ぐために情報を共有することもあります。
クロスボーダー税制は、国際的なビジネスが公平に行われ、各国が適切に税金を集められるようにするための大切なルールなんです。
次の円安のピークは2032年くらい、その時は1ドル200円くらいだと思う
「次の円安ピークが2032年頃で、その時は1ドル=200円くらいになる」という予測 について、考えてみたいと思います。
2032年に1ドル=200円の可能性はあるのか?
円安・円高の動きは 「日本とアメリカの経済状況」「金利差」「国際情勢」 など、さまざまな要因によって決まります。
もし、2032年に1ドル=200円になっているとしたら ①日米の金利差がさらに拡大
➡ 日本が低金利のまま、アメリカが高金利を維持すると、円が売られドルが買われる流れが続く。
日本の経済成長が停滞
➡ 日本のGDP成長率が低迷し、海外投資家が「日本の円を持っていても魅力がない」と判断すると、円が売られる。
日本の貿易赤字が拡大
➡ 輸入(ドルが必要)が増え、輸出(円を稼ぐ)が減ると、円安が進みやすい。
アメリカの経済力がさらに強くなる
➡ ドルが「世界最強の基軸通貨」としての地位を維持し、円の相対的な価値が下がる。
「円安が進む要因」がこのまま続けば、2032年に1ドル=200円もあり得るかもしれません。
逆に、円高に戻る可能性はあるのか?
一方で、日本経済が回復し、円が強くなるシナリオも考えられます。
日本が金利を引き上げ➡ 日本が 金利を上げれば、円の魅力が増し、円高方向に動く。
日本の経済成長が回復➡ 日本企業が強くなり、投資資金が円に戻れば、円安が抑えられる。
世界的な金融危機で「円買い」が起こる➡ 円は「安全通貨」としての側面もあり、リーマンショックのような大きな危機が起こると、一時的に円高になることがある。
「円安が続く」と決めつけるのは難しく、経済環境次第で円高になる可能性も十分にある
「未来の為替を完璧に予測するのは難しい」ので、いろいろなシナリオを考えて投資や資産運用をすることが大切だなと感じています
SBIの入金の方法があまりわからなくて
SBI証券には大きく分けて3つの入金方法があります。
- 銀行振込→ 手数料がかかる可能性あり&反映に時間がかかる
- SBIハイブリッド預金(住信SBIネット銀行経由)→ 自動スイープ機能で便利
- 即時入金(ネットバンキング経由)→ 手数料無料&リアルタイム反映
即時入金
🔹 特徴
✅ 24時間365日OK!(メンテナンス時間を除く)
✅ 入金手数料が無料!
✅ すぐにSBI証券の口座に反映!
🔹 やり方
- SBI証券のサイトにログイン
- 「入出金・振替」→「即時入金」 を選択
- 利用可能なネット銀行を選び、入金額を入力
- 銀行の画面に移動するので、ログインして入金を確定
- SBI証券の口座に即時反映!
🔹 対応銀行
✅ 住信SBIネット銀行(おすすめ!)
✅ 楽天銀行
✅ 三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行
✅ PayPay銀行 など多数
住信SBIネット銀行なら「ハイブリッド預金」も使えてさらに便利
銀行振込(通常入金)
🔹 特徴
✅ 自分の銀行口座から振込で入金できる
✅ 手数料は銀行によって異なり、有料の場合も
✅ 入金反映は通常 翌営業日 になることが多い
即時入金が使えない場合の代替手段
🔹 やり方
- SBI証券の「振込先口座情報」を確認(※口座ごとに専用の振込先がある)
- 自分の銀行口座から指定の口座へ振込
- SBI証券の口座に反映されるまで待つ(通常、翌営業日)
振込手数料がかかる場合があるので、即時入金のほうがおすすめ
銀行振込でSBI証券に入金する方法
1. 準備するもの:
– お持ちの銀行のキャッシュカード
– SBI証券の口座番号
2. 銀行のATMに行きます。
3. ATMにキャッシュカードを入れて、暗証番号を入力します。
4. 「振込」または「振替」のボタンを押します。
5. 振込先としてSBI証券を選びます。初めての場合は「新規」で登録が必要です。
6. SBI証券の口座番号を入力します。
7. 振り込む金額を入力します。
8. 確認画面で内容を確認し、よければ「確定」を押します。
9. お金と利用明細書を受け取ります。
注意点:
– 手数料がかかります。金額は銀行によって異なります。
– お金がSBI証券の口座に反映されるまで、数時間かかることがあります。
– 夜間や休日に振り込むと、翌営業日に反映される場合があります。
この方法は簡単ですが、手数料がかかり、すぐにお金が使えないことがあります。急いでいない場合におすすめです。
SBIハイブリッド預金(住信SBIネット銀行経由)
🔹 特徴
✅ SBI証券と住信SBIネット銀行を連携すると、自動で資金を移動できる
✅ 銀行口座の残高をそのまま投資に使えるので、手動入金不要
✅ 預金金利が通常の銀行よりも高め(年0.01%〜0.02%)
SBI証券を使うなら、住信SBIネット銀行の口座を作っておくと便利
やり方
- 住信SBIネット銀行に口座を開設
- 「SBIハイブリッド預金」に資金を移動
- SBI証券で自動的に資金を利用可能
「自動スイープ機能」を使えば、証券口座と銀行口座の資金移動がスムーズ
おすすめの入金方法
| 入金方法 | 手数料 | 反映時間 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| 即時入金 | 無料 | リアルタイム | ★★★★★(最優先!) |
| 銀行振込(通常入金) | 銀行による(有料の場合あり) | 翌営業日 | ★★☆☆☆(即時入金できない場合のみ) |
| SBIハイブリッド預金 | 無料 | リアルタイム | ★★★★★(住信SBIネット銀行ユーザーなら最適!) |

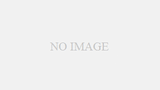
コメント