AIが「当たり前」になる未来
- AI技術は急成長していて、いずれ生活に完全に馴染んでしまう。
- 2050年になっても「AIすごい!」とはならず、冷蔵庫や電気と同じように当たり前の存在になる。
と言われていて、資料作成などに役立てたり、生活で使いこなしている人が出てきました。
AIで仕事がなくなるか
「AIにクリエイティブなことをやらせるのではなく、家事を任せるべき」
つまり、人間がやるべきことは創造的な仕事や、考えること。AIやロボットは雑用をやる存在なので、掃除・洗濯・料理など、生活のサポートをしてくれるAIが理想的という話には、多くの人が共感できるのではないでしょうか。
AIが株式市場を変える日が来る?
- AIが株を完璧に分析するようになると、個人投資家が勝てなくなる世界が来るかもしれません。
- 今の株式市場は「情報の非対称性(=知ってる人だけ得する)」があるから動いている。
- でもAIがすべての情報を即座に分析できると、その差がなくなってしまう。
最終的には、市場価格が動かなくなる=セカンダリーマーケットが機能しなくなるという未来もあり得ると言われています。
宇宙ビジネスは「経済」より「国家のプライド」
最近盛り上がっている宇宙産業
- 宇宙開発は「マネタイズ目的」というより、アメリカと中国の国家間のプライドをかけた戦い。
- 唯一、ビジネスとして収益を生んでいるのは衛星通信(イーロン・マスクのスターリンクなど)。
さらに、火星や月の資源が現実に運ばれるようになると、貴金属の価格が暴落したり、地球経済に影響が出る可能性もあると指摘。
人間の価値が問われる時代
AIが進化していく中で、最も懸念するもの
「人間が“無価値”と見なされる未来」
歴史を振り返ると、人の命や労働が大切にされるようになったのは、疫病などで人口が減ったときです。逆に、AIによって人間の価値が低くなれば、民主主義や人権の根底が揺らぐ可能性もあると言われています。
子どもたちはすでに「メタバース世代」
- 子どもたちはオンラインゲームでアバター同士が出会い、チャットし、建物を作るなどを当たり前のようにこなしている。
- デジタル空間は、リアルな世界と同じように価値のある場所になっている。
実際、デジタル課金(たとえばスマホゲームのカードパックなど)は、物理的なモノがなくても経済が回ることを証明しています。
空飛ぶ車やドローンの未来
- 「空飛ぶ車」は技術的には可能だが、安全性や事故リスクの懸念が高い。
- 日本のような国では、1度の事故で世論が一気に反対に回る可能性が高い。
- 逆に、田舎でのドローン配達などは現実的で、すぐに実現する可能性がある。
インフレと日本人の価値観のズレ
「長年デフレだった日本では、インフレになっても行動が変わらない人が多い」
今後インフレが進む中で、お金の考え方や資産運用の感覚をアップデートする必要があると言われています。
まとめ
AIやテクノロジーの進化は止められないという現実。でも、その中でどう生きるか、どう選択するかが問われる時代に。
- AIを「使う側」になるのか、「使われる側」になるのか
- リアルの世界に価値を置くのか、デジタル空間に賭けるのか
- 国の競争の中で、私たち個人はどう生き抜くのか
どれも簡単な問いではありませんが、今からしっかり考えておくことで、2050年の未来を「自分らしく」迎えることができるかもしれません。

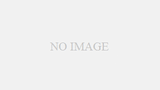
コメント