1930年代アメリカ:スムート・ホーリー法と株価の暴落
- 背景:1929年のウォール街大暴落(ブラック・サーズデー)を受けて、アメリカは保護主義政策を強化。1930年にスムート・ホーリー関税法を施行。
- 内容:外国製品に非常に高い関税を課すことで、アメリカ国内の雇用と産業を守ろうとした。
- 結果:
- 各国が報復関税を実施。
- アメリカの輸出は半減(約-50%)。
- 世界の貿易量が激減し、世界恐慌が深刻化。
- 株価は1929年のピークから約90%下落(ダウ平均:381ドル → 41ドル台へ)。
つまり、関税戦争が国際貿易と市場心理を冷え込ませ、株価を暴落させたという流れです。
トランプ政権の関税政策との比較
- 2018年以降、トランプ政権は中国製品を中心に高関税をかけ、世界的な関税摩擦を引き起こしました。
- その際も市場では「1930年代の再来か?」と不安視され、短期的には株価が調整しました(例:2018年2月のVIXショックなど)。
- しかし、当時と違い世界の中央銀行(FRBなど)は即座に金融緩和で対応したため、株価は長期的に回復しました。
ここが1930年代との違いです。
戦後の日本のインフレ
終戦直後(1945年〜1950年頃)
- 戦後の日本は物資不足と統制経済の崩壊によって、猛烈なインフレに直面しました。
- 具体的には、1946年の消費者物価指数(CPI)は前年比で約+567%上昇(6.7倍)しました。
- 1945〜1949年の間に、物価は約70倍以上になったと言われています。
インフレ率の推移
| 年 | 消費者物価指数(CPI)前年比増加率 |
|---|---|
| 1945年 | +237% |
| 1946年 | +567% |
| 1947年 | +83% |
| 1948年 | +48% |
| 1949年 | +11%(安定化) |
1949年のドッジ・ライン(財政引き締め)**以降はインフレが抑制され、安定成長期へと移行します。
まとめ
- 1930年代のアメリカは保護主義と関税戦争によって、株価が90%近く下落し、世界恐慌が悪化した。
- トランプ時代の関税政策も一時的に市場の不安を煽ったが、現代は政策対応が早く、致命的な株価崩壊には至らなかった。
- 戦後の日本は、終戦直後に年500%超のインフレを経験したが、財政・金融政策によって短期間で安定化。
歴史の知識は、今の投資判断やニュースへの理解にも大きな力になりますね。
参考:
- 『戦後経済史』野口悠紀雄(東洋経済新報社)
- FRB Historical Data
- 総務省統計局「消費者物価指数(CPI)長期時系列」
投資を始めるならネット証券NO.1のSBI証券が最適です。
SBI証券
https://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100piab00nwdu
起業するなら確定申告はマネーフォワードクラウドが簡単です。
マネーフォワードクラウド
https://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100piab00nwdu
自分の強みを活かした個性を売るならココナラが最適です。
https://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100piab00nwdu
chatGPT無料
https://chatgpt.com/
情報源がわかるai
perplexity ai
音楽を作ってくれるai
https://suno.com/

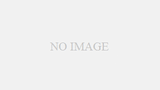
コメント