ヒューマンエラーとグラスコックピット依存の可能性
グラスコックピット(電子計器)は、最新鋭の航空機で標準となっている装備です。多くの情報を一つの画面で提供し、ナビゲーション支援や警告表示など安全性向上を目的としています。しかし同時に、その利便性が「新たなリスク」を生み出していると過去の研究で指摘されています。
1. 注意のトンネリング(Attention Tunneling)
・パイロットがコックピット内のナビゲーションディスプレイ(ND)やマルチファンクションディスプレイ(MFD)で誘導路情報や滑走路情報を確認していた可能性。
・これにより、実際の外部環境(エッジライトの位置や視界状況)への注意が散漫になった可能性。
→ 過去の事故調査では、「グラスコックピットへの過集中」によって外界への注意が低下する事例が複数報告されています(特に夜間や視界不良時)。
2. 認知負荷の増大と情報過多(Information Overload)
・グラスコックピットは大量の情報を同時に表示するため、必要な情報(例:現在地、誘導路の幅、障害物)を素早く取捨選択する負荷が高い。
・特に夜間や複雑な空港(羽田のような誘導路が多い空港)では、情報過多による「見逃し」や「遅延判断」が発生しやすい。
3. 自動化への過信(Automation Bias)
・航空機のFMS(フライトマネジメントシステム)やNDで表示されるルートに沿って走行していることで、実際の視界確認や目視確認が疎かになるリスク。
・「システムが正しいはずだ」という心理(Automation Bias)が、ヒューマンエラーの引き金になるケースが多いと報告されています。
まとめ
今回のJAL377便の事故は、重大な人的被害がなかったものの、航空安全の本質的課題を改めて浮き彫りにしました。
特にヒューマンファクターの観点からは、
「高度なシステムがあっても、人間の注意・判断・行動が安全の最後の砦」
であることを再確認すべき事例です。
グラスコックピットは確かに便利で安全性を高めるツールですが、過信や誤用は逆にリスクを高めることになります。
航空業界では、今後さらに「人と機械の役割分担」「人間中心設計」「ヒューマンファクター教育」の強化が求められるでしょう。
今回の事故の教訓とヒューマンファクター視点での考察
| 観点 | 課題 | 今後の対策 |
|---|---|---|
| グラスコックピット依存 | コックピット内情報への過集中 | 外界への目視確認を優先する手順の再確認 |
| 認知負荷 | 情報過多による判断遅れ | 情報の優先順位付け・フィルタリング技術の改善 |
| 自動化への過信 | システムの情報に頼りすぎ | マニュアル確認やクロスチェックの徹底 |
関連参考文献
- NASA Human Factors Report(https://human-factors.arc.nasa.gov/publications/)
- Flight Safety Foundation(https://flightsafety.org/)
- CASA Human Factors in Aviation(https://www.casa.gov.au/)

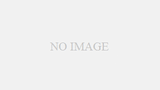
コメント