コアはS&P500、配当が欲しければサテライトでSCHDを足す
まずは前置きとして——
「新SCHD(楽天・SBIなどの国内投信)」と「米国SCHD(Schwab U.S. Dividend Equity ETF)」は中身ほぼ同じ”でも、 上場場所・買い方・手数料・税制が大きく違います。
違いのポイント
| 比較項目 | 米国SCHD | 新SCHD(楽天・SBI等) |
|---|---|---|
| 運用主体 | 米国上場ETF(シュワブ社) | 日本の公募投信(楽天投信・SBIアセマネ 等) |
| 購入可能場所 | 国内では原則 直接買付不可(米国ETFのSCHD) | 日本の証券会社で購入可。新NISA「成長投資枠」対象 |
| 最低購入額 | 1株単位(USD建て) | 100円〜積立OK(円建て) |
| 分配金 | 年4回(ETFの配当) | 年4回(投信の決算型。楽天は2/5/8/11月、SBIは3/6/9/12月) |
| 課税方式 | 米国源泉税+日本課税(二重課税。確定申告で外国税額控除の調整) | 国内投信課税(投信の二重課税調整の枠組み。取り扱いは目論見書等を確認) |
| 手数料 | 経費率 0.06% | 信託報酬 約0.1227〜0.1238%(実質で本家ETFコストも内包) |
| 購入手続 | 外貨(USD)建て | 円建て・手続き簡便 |
| ポイント等 | なし | 楽天は残高ポイント対象、SBIは投信マイレージ対象 など |
補足
- 運用の実態は近い:どちらもDow Jones U.S. Dividend 100に連動するSCHDを実質的に使います(投信はファンド・オブ・ETFの形)。
- コスト差の正体:国内投信は“投信の信託報酬”に本家ETFの経費が乗って実質コスト約0.12%台。それでも個人の実務(円建て・自動積立・税処理の簡便さ)という手間賃が含まれると考えると腑に落ちます。
- 税制・受け取り通貨:米国ETFはドル受け取り・確定申告前提になりがち。国内投信は円建て管理で、投信の二重課税調整の枠組みが適用される点が異なります。
以上を踏まえると、「国内で手軽にSCHDの性質を取り込みたい=新SCHD(楽天・SBI)」「純コスト最安&本家を直に保有したい=米国SCHD直買い」という使い分けになります。
この前置きの上で、S&P500 vs SCHD(コアはS&P500、配当重視はSCHDをサテライトに)の本編に続きます。
まず中身の違い
- S&P500:米国大型株の時価総額加重。超低コスト(例:VOOの経費率0.03%)で米国の広い成長を丸ごと取りにいくコア商品。足元は「マグニフィセント7」などメガテック比重が3割超まで高まっており、成長の恩恵も集中リスクも併せ持ちます。(investor.vanguard.com, フォーブス, フォール)
- SCHD:配当と財務クオリティを重視する高配当×連続増配寄りのファクターETF。Dow Jones U.S. Dividend 100 Indexをトラックし、経費率0.06%。セクターはディフェンシブ・バリュー寄りになりやすい。
どっちが“いいか”は目的次第
- 長期の資産最大化が第一(20年積立・再投資が前提)
→ S&P500中心。市場の勝者に自然と比重が乗る設計で、超低コスト。集中リスクはあるが、長期で米国経済の“総合点”を取りにいく戦略に合う。 - 毎年のキャッシュフロー(配当)を取りたい/価格変動にメンタルを左右されやすい
→ SCHDをサテライトで併用。分配金は相対的に高く、ディフェンシブ寄り。ただし成長相場(テック主導)ではS&P500に劣後しやすい局面もある点は理解を。 - 集中リスクが気になる
→ S&P500一本でも十分王道だが、比重がテックに偏っていることは事実。ポートフォリオ全体でバランスを意識(例:一部をSCHDや現金・債券に)
配分の目安(例)
- 成長ガチ勢:S&P500 100%
- 中庸(増配も欲しい):S&P500 70% + SCHD 30%
- 配当重視:S&P500 50% + SCHD 50%
(NISA枠・税制や生活目標に合わせて微調整)
実務のワンポイント
- コスト:経費率の差は複利で効きます(VOO0.03%、SCHD0.06%)。
- 課税:米国籍ETFの分配金は源泉徴収あり。居住国の税制・NISA利用可否で手取りは変わります(具体の税率は各自の状況で要確認)。
- リバランス:目標配分を年1回などで淡々と調整。
- メンタル適合:配当で“見えるリターン”が心地よい人はSCHDを少量足すだけで継続力が上がることも。
まとめ
- 王道はS&P500=コア。
- 配当という現金フローが欲しいならSCHDをサテライトで。
- どちらも低コスト・ルール明確。自分の目的(成長か配当か)と継続しやすさで決めるのが正解。
2025年8月27日時点のSCHD(Schwab U.S. Dividend Equity ETF)公式保有一覧から、代表的な30社
- Chevron(CVX/シェブロン)
- ConocoPhillips(COP/コノコフィリップス)
- Altria Group(MO/アルトリア)
- PepsiCo(PEP/ペプシコ)
- AbbVie(ABBV/アッヴィ)
- Home Depot(HD/ホーム・デポ)
- Merck(MRK/メルク)
- Texas Instruments(TXN/テキサス・インスツルメンツ)
- Cisco Systems(CSCO/シスコシステムズ)
- Verizon Communications(VZ/ベライゾン)
- Amgen(AMGN/アムジェン)
- Bristol Myers Squibb(BMY/ブリストル・マイヤーズ スクイブ)
- Coca-Cola(KO/コカ・コーラ)
- Lockheed Martin(LMT/ロッキード・マーティン)
- EOG Resources(EOG)
- United Parcel Service Class B(UPS/UPS)
- Fastenal(FAST/ファステナル)
- Schlumberger(SLB/シュルンベルジェ)
- ONEOK(OKE/ワンオーク)
- Ford Motor(F/フォード)
- Valero Energy(VLO/バレロ・エナジー)
- Paychex(PAYX/ペイチェックス)
- Target(TGT/ターゲット)
- Kimberly-Clark(KMB/キンバリー・クラーク)
- Archer Daniels Midland(ADM/アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド)
- Fifth Third Bancorp(FITB)
- Hershey(HSY/ハーシー)
- General Mills(GIS/ゼネラル・ミルズ)
- Regions Financial(RF)
- Darden Restaurants(DRI/ダーデン・レストランツ)
※組入れ銘柄は適宜見直し・入れ替えが行われます。最新はSchwab公式の保有一覧でご確認ください。
指数は?
Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(ダウ・ジョーンズ米国配当100)。SCHDはこの指数への連動を目指します。
入れ替わり(見直し)の“タイミング”
- 年1回のリコンスティテューション(構成見直し):銘柄の入れ替え・採否を判定。
- 四半期ごとのリバランス:採用後のウエイト(比率)調整だけを行う。
- 上限ルール:1銘柄4.0%以下/1セクター25%以下(見直しやリバランスの時点で適用)。
これらはSCHDの目論見書に明記されています。
採用“基準”(スクリーニングとスコアリング)
指数の母集団はDow Jones U.S. Broad Market Index(REIT、MLP、優先株・転換社債などは除外)。その上で——
- 10年以上連続で配当を支払っていること
- 浮動株調整後時価総額 5億ドル以上+流動性基準を満たすこと
- 4つの“質×配当”指標で総合評価
– キャッシュフロー/総負債
– ROE(自己資本利益率)
– 配当利回り
– 5年配当成長率 - 採用後は**“修正・時価総額加重”**でウエイトを付与(=大型で評価の高い銘柄に比重が乗りやすい)。
以上も同じく目論見書で定義されています。
“どんな風に”入れ替わるの?
- 年次見直しで、上の基準を満たせなくなった銘柄は除外、満たした新顔が追加。
- 四半期リバランスでは、価格変動や配当・業績の変化で比率だけ調整(上限ルールに合わせる)。
- 実例:2025年の年次見直し後、指数の採用・ウエイト調整の結果としてエネルギー比率が大きく上昇(SCHD全体のエネルギー・エクスポージャーが約21%へ、最大保有はCOP・4.7%近辺)。市況や基準適合の結果として、こうしたセクター偏りが起こることがあります。
投資家目線でのチェックポイント
- 構成は“毎年変わる”前提:減配・財務悪化・株価急騰/急落で採用/除外・比率が動く。
- 分散と偏りのバランス:4%/25%の上限で“集中し過ぎ”は抑制するが、相場局面により特定セクターが重くなることはある。
まとめ:SCHDは「10年配当+質スコア」で100銘柄を選び、年1回入替・四半期ごとに配分調整。 ウエイト上限のガード付き“クオリティ高配当”戦略です。

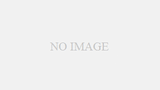
コメント