日本の家計環境は、これまで以上に逆風を受けています。
少子高齢化、社会保障費の増大、賃金停滞、インフレ——。
そんな時代を生き抜くために、私たちは「稼ぐ力」よりも先に**“貯める力”**を鍛える必要があります。
日本の家計を取り巻く現実
高齢化と社会保障費の爆増
- 2025年:団塊世代が75歳以上に
- 2070年:65歳以上人口比率が約40%
- 社会保障給付費は現在137兆円 → 将来180兆円超の予測
年金の目減り
- 所得代替率は現在61% → 2057年には50%前後に低下
- モデルケース:月23万円 → 約19万円へ減額見込み
インフレと実質賃金低下
- 過去30年で物価は大幅上昇(牛丼290円→500円、ガソリン88円→180円)
- 平均年収は457万円(1995年)→ 426万円(2024年)
お金持ちになる人と貧しくなる人の二極化
資産分布の調査(野村総研「富裕層ピラミッド」)によると、
- 富裕層(1億円以上)は年々増加
- マス層(3,000万円未満)も増加
- 中間層(3,000万〜5,000万円)は減少
つまり、「戦略的にお金をコントロールできる人」と「お金にコントロールされる人」に分かれています。
貯める力の基礎は「家計の見える化」
家計管理の4ステップ
- 現状把握
- 家計簿や家計アプリ(例:マネーフォワードME)で自動記録
- 収入、固定費、変動費、特別費に分類
- 価値観の明確化
- 「譲れない支出」と「不要な支出」を仕分け
- 無意識の支払いを削減
- 予算設定
- 月次予算と週次予算を設定(特に変動費は週単位で管理)
- 振り返りと改善
- 毎月仕訳を見直し、翌月に反映
家計簿アプリを“通帳代わり”にしてしまうことは注意しましょう。データは“見るだけ”でなく、仕訳を修正し改善に使うことが重要です。
固定費削減の優先順位
固定費の見直しは、効果が持続するため最優先です。
優先度は以下の順番が効率的。
- 保険(収入保障保険以外は原則不要)
- 必要なのは「確率は低いが損害が大きいリスク」だけをカバーする保険
- 医療保険は原則不要。加入するなら県民共済(入院型)がコスパ最強
- 住宅費(家賃・住宅ローンの見直し)
- 通信費(格安SIM・光回線の再契約)
- 自動車関連費(任意保険・車両維持費)
- サブスク・その他契約
ライフプランニングで未来の支出を可視化
ライフプランとは「将来の家計カレンダー」。
教育費・住宅費・老後費用という三大支出を時系列で整理し、10年先までの現実的な計画を立てます。
- 住宅費:賃貸か購入か、新築か中古かを含め総額試算
- 教育費:公立中心で1,000万円〜、私立中心なら2,500万円以上
- 老後費用:生活費×年数+医療・介護費用(目安3,000万円)
貯めたお金の使い道は「投資」と「浪費」に分ける
- 消費:生活に必要な支出
- 浪費:生活に不要だが幸福感を得る支出(意識的に)
- 投資:将来の収入や価値を生む支出
収入から消費を引き、残った利益を「投資」と「浪費」に振り分ける。
浪費も悪ではなく、“計画的な浪費”なら人生の満足度を高めます。
実践の第一歩
- 家計簿アプリで全口座・カードを連携
- 固定費から順番に見直し
- ライフプラン表を作成
- 浪費は「利益の範囲」で楽しむ
まとめ
お金にコントロールされる人生から、お金をコントロールする人生へ。
貯める力は資産形成の1丁目1番地であり、稼ぐ力や増やす力の土台です。
「現状把握 → 固定費削減 → ライフプランニング → 投資」の流れを作れば、将来の不安は大きく減らせます。

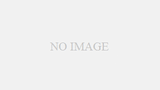
コメント