グラスコックピットが招くパイロットのミス
近年の航空機は「グラスコックピット」と呼ばれる最新型の電子表示システム(デジタルディスプレイ)を搭載しています。これにより操縦席の情報量は飛躍的に増え、飛行データの一元管理や効率的な操作が可能になりました。

Screenshot
しかし、こうした技術進歩の一方で、人的ミス(ヒューマンエラー)による新たなリスクが指摘されています。2025年4月7日の羽田空港でのJAL機接触事故や、2024年のJAL516便滑走路衝突事故は、その典型例と言えるでしょう。
問題点① 外部視界確認の機会が減少
グラスコックピットの最大の問題は、パイロットが「計器に頼りすぎてしまう」ことです。地上走行や離着陸時、本来パイロットは目視で滑走路や誘導路の状況確認を行う必要があります。しかし、ディスプレイ上の情報が豊富になると、自然と視線が計器内に集中し、外部状況の確認がおろそかになる傾向があります。
→ 羽田JAL機の事故では、地上走行中に誘導路脇の航空灯火(エッジライト)に接触しています。これは外部目視が十分でなかった可能性を示唆しています。
問題点② 夜間・悪天候時の視認性悪化
夜間や雨天時は、滑走路や誘導路の灯火が乱立するため、目視による位置確認が難しくなります。特に、HUD(ヘッドアップディスプレイ)やナビゲーションディスプレイを多用すると、小さな障害物(例えばライトや小型機)は背景に埋もれてしまいます。
→ JAL516事故でも、滑走路上にいた小型機(海上保安庁のDash 8)をパイロットが目視できなかったことが問題となりました。
問題点③ HUDやディスプレイ依存による状況認識低下
最新のHUDは高度な情報を表示しますが、その分、視線や意識がHUD内部に閉じ込められがちです。これが逆に外部の状況(障害物や他機)への注意散漫を招くことがあります。
→ HUDはあくまで補助装置であり、本来は外部目視との併用が前提ですが、運用実態ではHUD依存が進んでいる懸念があります。
問題点④ 期待バイアス(Runway Clear Assumption)
パイロットは「滑走路や誘導路はクリア(安全で障害物なし)」であるという前提で行動する傾向があります。特にグラスコックピット化が進むと、外部の異常検知よりもシステム情報に依存する割合が高くなり、不測の事態への対応が遅れやすくなります。
→ 羽田のJAL377機接触事故でも、誘導路に障害物(灯火)があるとは思わず走行してしまった可能性があります。
問題点⑤ 緊急時対応の遅延
状況認識が遅れると、異常発見から回避行動までの時間が不足します。これは接触事故や衝突事故を招く要因になります。
→ JAL516事故ではDash 8機の存在に気付いた時点で、既に衝突回避は不可能だったとされています。
まとめ
最新のグラスコックピットは航空安全に多大な貢献をしていますが、その運用方法を誤れば、新たなヒューマンエラーの温床となります。特に外部視界確認の徹底と、HUD・ディスプレイの適切な活用が重要です。
今後、航空業界では次のような対策が求められます。
- パイロットの外部視認訓練(夜間・悪天候対応含む)
- HUDやグラスコックピットの適切な運用指導
- 誘導路・滑走路のインフラ改善(視認性向上)
- 地上走行時の状況認識能力(SA: Situational Awareness)の強化
このように、技術と人間のバランスを取ることが、真の航空安全につながるのです。

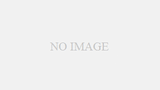
コメント