極東証券(8706)の評価
① 配当性向・配当利回り(持続性・魅力)
- 2024年3月期に1株110円と前期比3.6倍に増配し、**予想配当利回りは約7.9%**という魅力的な水準。(ダイヤモンド・オンライン, 北日本.com)
- 配当性向および総還元性向は約78.9%。利益の多くを配当に回す方針が透けて見えます。(北日本.com)
- 売上高+79%、営業益黒字転換、経常益7.5倍、EPSは3.7倍に拡大と、業績の急回復が背景にあります。(マネーポストWEB)
- 財務は堅実で、有利子負債倍率は0.21倍と低水準。自己資本厚調で信用力も悪くありません。(マネーポストWEB)
まとめ:短期的には高配当の魅力と業績改善で魅力がありますが、「高配当性」が続くかは利益基盤と方針次第。配当性向が高いため、業績が悪化すると減配リスクも。
東洋証券(8614)の評価
② 信用力・配当の持続性
- Simply Wall St によると、配当は「利益の約37%」であり、配当を利益内で賄い、比較的持続可能と評価。過去5年のEPSは年率+10%で成長中。(Simply Wall St)
- 一方、過去10年の配当は年平均で1.8%の減少傾向。配当自体は減ってきているので注意。(Simply Wall St)
- 財務面では、行政処分の過去や利益水準の不安定さ、内部留保の少なさが課題として指摘されています。2023年3月期は売上が前年比+44%増、しかし営業利益は2019年水準を下回っており、利益の脆弱さが懸念です。
- 配当性向は**305%**と異常に高く、内部留保を前借りして配当した可能性があり、中長期的な持続性には疑問。
まとめ:一時的に増配が好材料ですが、行政リスクや利益基盤の脆弱さ、過度な配当性向が「高配当維持の信頼性」を揺るがします。
共通リスク(東証セクターや政治・経済外部要因視点)
③ 地政学的リスク・関税リスク
- 特にトランプ関税など米国との摩擦や通商リスクが高まると、輸出関連ではなくとも日本全体の金融市場に影響が及ぶ可能性あり。証券会社への間接的影響も警戒必要。(野村証券)
- 内需・対面営業中心の極東証券は影響軽微かもしれませんが、東洋証券の米国株依存など収益構造次第でリスクとなる可能性あり。
④ 流動性・価格変動リスク
- 東洋証券や極東証券単独への大量投資は、流動性の限界によって売買が不利になる場合があります。投資信託レベルでの組み込みも慎重に。(toyo-sec.co.jp, APL Wealth Advisor)
- また、株式市場・金利・為替の変動によって価格が上下する「価格変動リスク」や企業業績の悪化による「信用リスク」にも注意が必要です。(toyo-sec.co.jp)
比較・ポイント早見表
| 銘柄名 | 魅力・強み | 主なリスク |
|---|---|---|
| 極東証券 | 業績急回復 & 高配当(7.9%)財務安定(負債低) | 配当性向高め(78.9%)米リスク等外部ショック |
| 東洋証券 | 配当が利益内(配当性向約37%)EPS年10%成長 | 過去の行政処分・利益脆弱高すぎる配当コスト(305%) |
まとめ
- 極東証券は「業績がガツンと良くなって高配当でお得!しかも財務もしっかりしてるよ」という魅力ある銘柄。ただし「急な業績悪化で配当が急に切られるかも?」という心配もあるので、ほどほどの分量で持つのが吉。
- 東洋証券は「利益の中で無理なく配当するタイプで、EPSも伸びているし安心感あるよ」と見える反面、行政処分や利益の底力の弱さ、そして配当の出しすぎ(自分の懐から出してるようなもん)が裏目に出るリスクもあるので、慎重に判断を。
さらに地政学リスクや世界のルール変化(関税・経済摩擦など)を考えると、ディフェンシブな内需・安定業種との分散投資でリスクを抑えるのがオススメです。

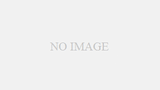
コメント